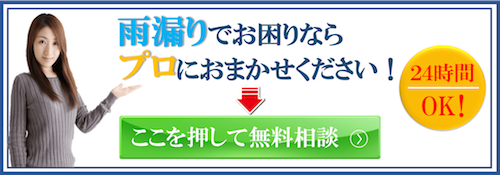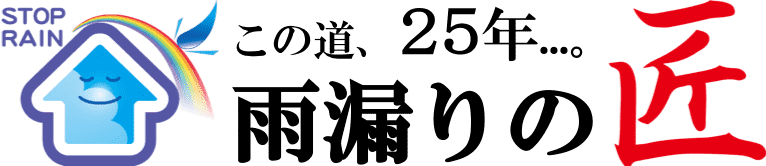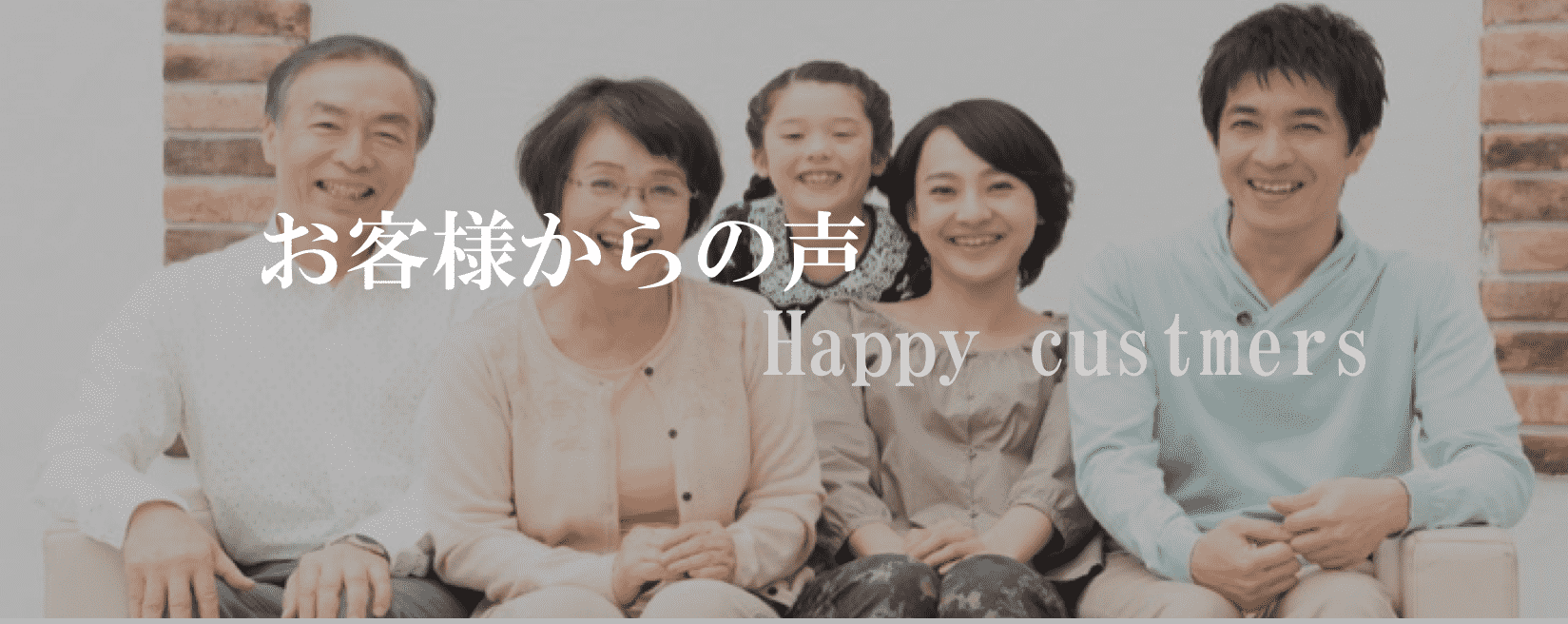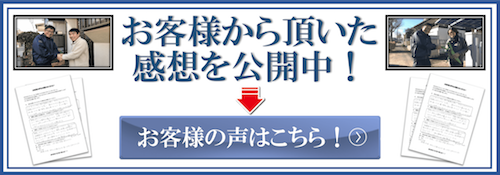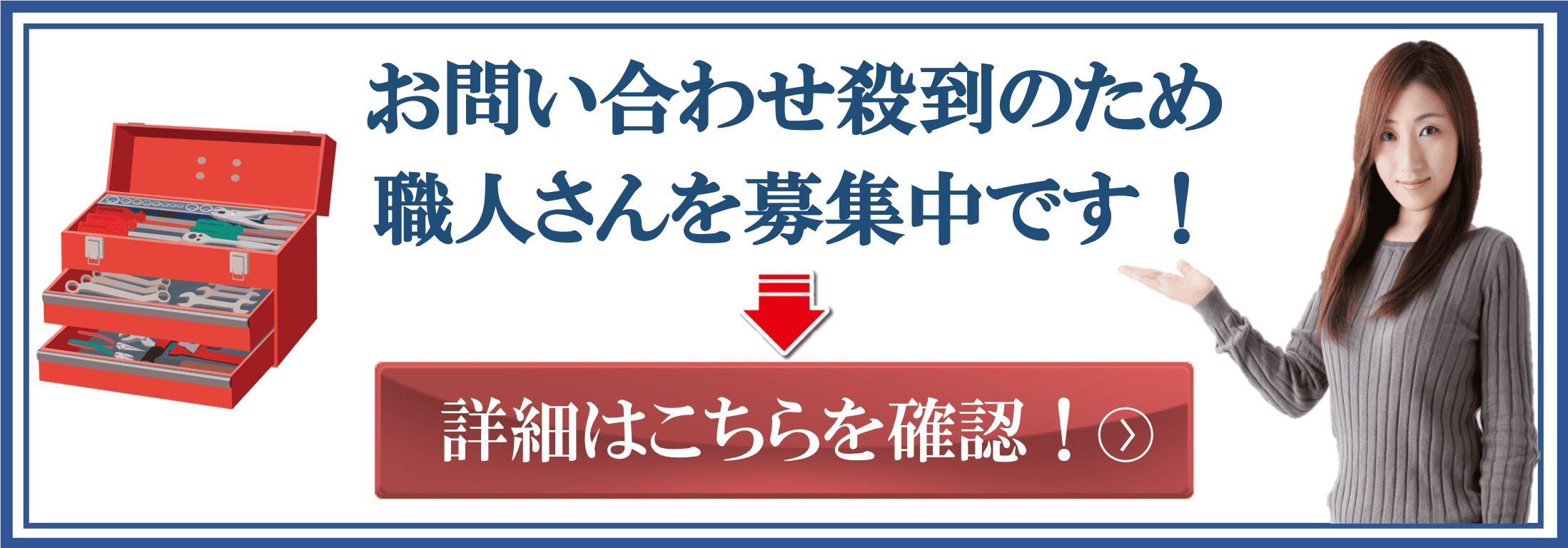- 差し掛け屋根で特に注意すべき雨漏りの注意点
- 差し掛け屋根で起こり得る雨漏りケース
- 雨漏りが発生した際の基本対策
このような記事を書いておいてなんですが…。
『差し掛け屋根』と聞いても、あまりピンとこない方の方が多いかも知れません(汗)。ですが、じつは住宅での採用率が高く、関係している方も多い屋根なんですよ。
なぜなら、差し掛け屋根は…切妻屋根や寄棟屋根など様々な屋根と組み合わせる”サブ的な働きをする”屋根。ですから、あまり名称自体は知られてはいないんですが、現状として、たくさんの住宅に差し掛け屋根は採用されています。
多く採用されるのは、当然ながら『メリットがある構造だから』ですが…じつは差し掛け屋根は少し特殊な構造をしており、『雨漏りが起きやすい』といったデメリットもあるんですよね。
そこで、この記事では差し掛け屋根について”雨漏りの専門家観点”を軸にまとめてみました。
【前提知識】差し掛け屋根の基本構造

「そもそも差し掛け屋根ってどこ?ウチは関係あるの?」
と思ったかも知れません。じつは、『2階建て住宅の1階部分の屋根』を差し掛け屋根と言います(下屋と呼ばれることもあります)。
- 2階の屋根→大屋根(メインの屋根、切妻屋根など)
- 1階の屋根→差し掛け屋根、下屋(サブの屋根)
といったイメージ。
差し掛け屋根の重要な特徴
『外壁に直接取り付けられている』のが差し掛け屋根の大きなポイント(ですから、形的には片流れ屋根であることがほとんどですね)。
構造的に『1階の外壁部分を差し掛け屋根が覆う形』となるため、外壁の劣化を防ぐことや、屋根下をスペースとしていろんな用途で利用できます。
ただ…この『外壁に直接取り付けられている』という点が、雨漏りを引き起こしやすい要因にもなっています。
次は、その要因についてお話していきましょう。
差し掛け屋根”特有”の雨漏り注意箇所

住宅には様々な形状があり、それによって雨漏りの起こりやすい注意箇所も変わってきます。
差し掛け屋根の最も注意すべき箇所というのは、『差し掛け屋根と外壁の取り合い部分』。ここがもっとも注意すべき箇所となります。
繋ぎ目はどうしても家屋の隙間ができやすい箇(雨水は、大体のケースでこの『隙間』から侵入してきますからね)。差し掛け屋根の特徴である、外壁に”直接”取り付けている部分が、まさに『弱点部分』となるんです。
たとえば…プラモデルって、一見隙間が無いように見えても、実際はパーツ同士を組み合わせてるので、実際は薄く隙間が空いてますよね。
これと同じで、差し掛け屋根と外壁には雨の通り道となる隙間が、構造上どうしてもできてしまうんですよ。さらに、差し掛け屋根はサブ的存在…メインである大屋根部分から外壁を通ってきた雨水が、取り合い部分に溜まりやすいという問題点も(汗)。
基本的に”雨仕舞”処理で保護されています
建てる側としても、取り合い部分が弱点となることはもちろん把握しています。ですから、『雨仕舞』という施工で、しっかりカバーを行っているのが基本。
ですから『差し掛け屋根は雨漏りに弱い』→『家屋に採用したら、即雨漏り!』なんてことはありません。この差し掛け屋根でいえば、取り合い部分には板金を設置し、流れてくる雨水を適切に排水できるよう作られています。
それでも、雨漏りが起きてしまう理由…それは、この『弱点部分に対するカバー』も、永久には続かないから…。
次は、差し掛け屋根で雨漏りする理由と原因をご説明します。
差し掛け屋根で雨漏りが起きる原因

その理由は、いわゆる『劣化』。
どのようなものにも耐用年数はありますので、『劣化が原因となる』雨漏りは、べつに差し掛け屋根に限った話ではありません。
ですが…差し掛け屋根は、構造的に『劣化で受けるダメージが大きい』んですよね(汗)。
- 雨仕舞のコーキング劣化
- 外壁の劣化
雨仕舞のコーキング劣化
雨仕舞として取り付けている板金にもどうしても隙間はできるので、その対策としてコーキング(部材同士の隙間を埋めるゴム状の素材)で隙間を埋めています。
しかしその効果も永久ではありません。残念ながら5~10年を目安に、経年劣化によって剥がれやひび割れなどの破損が起きてしまうんですね。
そこから雨水が侵入し、取り合い部分から雨漏りに繋がってしまう、という訳です。
雨仕舞がカバーしている箇所は…そう、まさしく『差し掛け屋根の弱点』そのものですよね。このコーキングが劣化してしまうと、弱点が晒されているようなもの。ですから、雨漏りする可能性が一気に爆増してしまうんです。
外壁の劣化
「ん?屋根の話じゃないの?」
と思うかもしれませんが…差し掛け屋根は外壁に直接取り付けられている屋根でしたよね。ですから、外壁問題は切っても切り離せないのです。

じつは”施工不良”なんてケースも…
あえてここは原因理由に挙げませんでしたが…悲しいことに、いわゆる『施工不良』が起きやすい箇所でもあるんですよね(汗)。
屋根にしても外壁にしても、表面の建材だけが防水しているわけではなく、じつは”内側の防水シート”も防水してくれているんです。
じつは、差し掛け屋根の施工時は、取り合い部分の隙間を塞ぐため、外壁にかけて防水シートを立ち上げて施工しなければいけません(基準として、250mm以上立ち上げる必要あり)。
ここにミスが起きやすいのです(いわゆる業者のミスや、知見不足による基準オーバーですね)。
こういった施工不良の場合は劣化では無いので、築年数も関係なく、たとえ新築であってもいきなり雨漏りしてしまう…といったこともあります(汗)。
ただし、施工不良は保証でかなりカバー可能!
少し話は逸れますが、新築で雨漏りが起きた場合は保証が効く場合もあります。
「劣化するほど期間も経ってないんだけど!」という場合は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

差し掛け屋根の雨漏りは、特にカビに注意!

差し掛け屋根の雨漏りリスクは取り合い部分に集中しがちですが、屋根材表面の劣化にも注意が必要です。
差し掛け屋根は外壁に直接設置されているため、付近の日当たりが悪くなります。結果、苔やカビが発生しやすいんですよ。
この苔やカビが屋根材表面の劣化を進めてしまうため、他の屋根に比べて早く劣化し、雨漏りリスクが高まる…という悪循環。
ですから、差し掛け屋根の取り合いばかりでなく、表面部分も注意して見る必要があります。

差し掛け屋根の雨漏り予防ポイント

ここまで、差し掛け屋根の雨漏り原因について説明してきました。それにより、少しネガティブな気持ちになった方もいるかもしれませんが、正しく対策をすれば雨漏りを未然に防ぐことも可能なんですよ。
雨漏りの予防に一番必要なのは、とにかく『定期的な点検』と『必要に応じたメンテナンス』。
つまり差し掛け屋根の場合、見るべきは当然『特徴上、リスクが高い』とご説明した次の3点!
- 取り合い部分のコーキングがヒビ割れなどしていないか?
- 差し掛け屋根周辺の外壁に、ヒビ割れなどはないか?
- 差し掛け屋根の表面(や影)に、カビが発生していないか?
ご自身でのチェックは、十分注意してください!
定期的に確認すべきポイントは、やはりすべて『高所』…シンプルに危険です(汗)。
うっかり足を滑らせたりすれば、ケガで済めばある意味まだいい方。最悪の場合は命の危険だってありえます。
事実、業者さんでも細心の注意を払い、しっかりとした装備で作業に臨みます(高所作業の場合、じつは厳密な『安全対策ルール』があるんです)。
非常にリスクを伴うので、場合によっては業者さんに依頼した方が安心かも知れません。
点検ポイントに問題が見つかったら…
この場合は、基本『ご自身での対応は考えずに、業者へ依頼』を検討してください。
先ほど挙げた”高所作業である”という点だけでなく、現状の問題が『雨漏り被害につながっているのか』を確認する必要があります。
ですが…なかなか『目に見える被害が出ていない状態で、雨漏り診断を行う』というのは、素人には(正直に言えば、プロでも)難しい行為です(汗)。
雨漏りは『目に見えない状態で、内部に被害が広がっているケース』があります。この場合、被害が表に出た時には『すでに内部がかなりダメージを受けてしまっている』というパターンが多々…。
せっかく定期チェックで早期に問題を発見できているわけですから、しっかりと対策して欲しいな、と!



差し掛け屋根の雨漏りにおいて最も注意すべき危険箇所とは?.まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。最後にここまでの内容をまとめていきましょう。
差し掛け屋根”特有”の注意すべき箇所は…⬇︎
差し掛け屋根と外壁の取り合い部分!
差し掛け屋根で雨漏りが起きる原因は…⬇︎
- 雨仕舞のコーキング劣化
- 周辺の外壁劣化
- 施工不良
差し掛け屋根の雨漏り予防ポイントは…⬇︎
- 取り合い部分のコーキングがヒビ割れなどしていないか?
- 差し掛け屋根周辺の外壁に、ヒビ割れなどはないか?
- 差し掛け屋根の表面(や影)に、カビが発生していないか?
チェックの結果、問題点が見つかったら…⬇︎
問題点が雨漏り被害にまで発展していないか、専門業者に調査依頼が吉。雨漏りは『目に見えない部分』でも発生する!
今回の記事、いかがでしたか?
「大切な我が家…雨漏りが心配!」という方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
ㅤ